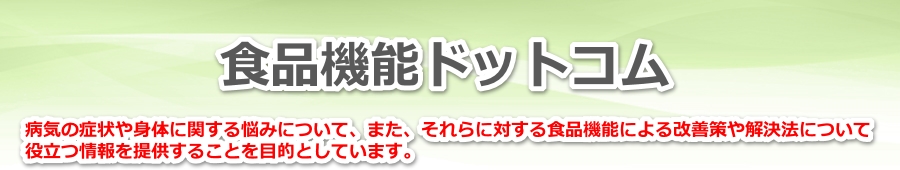プール熱で嘔吐や咳があるときの対処法と注意点!原因は何?
夏にプールに入り感染する「プール熱」の主な症状は、発熱やのどの痛み、目のかゆみや痛み、目やにといった結膜炎ですが、嘔吐や咳などの症状も現れることがあります。
なので、プール熱で嘔吐や咳の原因は何か、知っておきたいですよね。
また、こうした症状にはどのように対処したら良いのか、注意点は何かも気になりますよね。
そこで今回は、プール熱で嘔吐や咳があるときの対処法や注意点、原因について詳しくお伝えしていきます。
目次
プール熱で嘔吐や咳があるときの対処法と注意点!原因は何?
プール熱で嘔吐や咳の原因は?

プール熱に感染すると、まず急な発熱を起こし、続いてのどの痛みや、結膜炎による目の痛みやかゆみ、目やにや涙が止まらないといった症状が現れます。
ただ、のどの痛みが原因で咳が出たり、場合によってはウイルス性胃腸炎が原因となって、嘔吐をしたり下痢などの症状が現れることもあります。
そして、咳や嘔吐・下痢といった症状は、2次感染の場合が多く、子供からプール熱をうつされた大人の症状に多い傾向にあります。
この場合は、注意点に気をつけながら次のような対処法を行うようにしましょう。
プール熱の嘔吐や咳の症状への対処法と注意点は?

1) 病院で診断を受ける
プール病は手足口病など夏に多い他の感染症と原因となるウイルスが共通していることから、感染経路や症状などがとても似通っています。
そのため個人で見分けがつきにくいこともあるので、プール病の初期症状が現れたら、できるだけ早く病院で受診し、医師に診断してもらうようにしましょう。
ちなみに、プール熱は文科省指定の学校伝染病第2種の伝染病なので、感染すると学校などへの出席停止扱いになりますが、手足口病は指定外なので登校は可能です。
なので、できるだけ早く診断してもらうことで、症状の原因を理解した上で治療を行うことができ、患者の回復も早くなり、周りへの感染も防ぐことができます。
2) さらなる感染を防ぐ対処を行う
プール熱と診断されたら、まずは学校や保育園へ「傷病証明書」を送り、医師の診断に従って登校・登園を控えるようにしましょう。
ちなみに、社会人の場合は特に明確な出社停止基準は定められていないのですが、職場に相談し、少なくとも症状が治るまでは出社を控えると良いでしょう。
それから、プールに入った直後に感染した場合は、学校やスイミングスクールなどにもその旨を連絡すると、施設側が一時閉鎖するなど対処を行うことができます。
3) 感染を防ぎながら脱水症状対策も行い、免疫力をUPさせる
プール熱にはウイルスの対抗薬や予防のためのワクチンが存在しないため、体の中からウイルスが排出されるまで安静にして待つしかありません。
ただ、アデノウイルスは非常に感染力が強く、次の2つを経路として他者へうつるとされています。
・飛沫感染(ひまつかんせん)
くしゃみや咳、鼻水に含まれるウイルスに接触、または他者の口の中に入った場合に感染
・糞口感染(ふんこうかんせん)
便に含まれるウイルスが手などを経由して口の中に入った場合に感染
そして、アデノウイルスの潜伏期間は感染してから5~7日程度で、その後症状が現れ、さらに回復までは1週間程度とされています。
ただ、特に便に含まれるウイルスは1ヶ月後まで排出されるということなので、注意が必要です。
そのため、プール病にかかり、咳や嘔吐・下痢などの症状が出ていたら次の注意点を守りながら対処を行いましょう。
マスクを着用し、手洗いとうがいを徹底し、タオルは共用しない
くしゃみや咳で感染することを防ぐためマスクを着用し、手洗いやうがいも行いましょう。
また、口を拭いたタオルを他者と共用するだけでも感染するので、タオルは個人のものを使うなどの配慮が必要です。
プールに入ることや、お風呂へ他者と一緒に入ることは控える
糞口感染を招くので、プールはもちろん、家族内でも入浴を一緒に行うことは控えましょう。
ただ、夏はあせもケアもした方が良いので、プール熱にかかったら、せめて塗れタオルで汗や汚れを落とすか、シャワーのみにすると良いでしょう。
脱水症状対策を行う
嘔吐や下痢などの症状を伴うと、脱水症状にかかりやすくなるので、塩分や水分を同時に補給できるスポーツドリンクや経口補水液などをこまめに飲むようにしましょう。
その際、水だけでは脱水症状対策にならないので、水と共に梅干しを食べたり、塩分をとるよう意識することが大切です。
【Amazon.co.jp アソシエイト】
免疫力をUPさせる
ウイルスを排出しようと頑張っている体を完全に回復させるため、ウイルスに負けない免疫力の高い体作りをしましょう。
そのため、特に夏は量より質の食事を心がけ、鰻や長芋など、ビタミンや鉄分が豊富な食材を選び、薬味などでサポートしながらしっかり食べるようにしましょう。
4) 医師の診断を待ってから、登校・登園を再開する
症状が治ってから2日程度過ぎたら、病院で再度受診し、医師の診断を待って登校・登園を再開すると良いでしょう。
ただ、おむつ交換が必要な乳幼児の場合、糞口感染対策のために、保育園によって登園再開の基準を個別に設けている場合があるので、必ず確認するようにしましょう。
スポンサーリンク
プール熱にかかった時にオススメの食事はコチラ!

プール熱はのどの痛みも辛いですが、さらに咳や嘔吐などの症状が現れたら、食事や水分補給もできなくなってしまいますよね。
ただ、体の回復のためには栄養補給は必須で、特に嘔吐をしているときは脱水症状にならないようできる限りこまめな水分補給を行うようにしましょう。
そのため、プール熱にかかった時にオススメの食事は次の通りです。
1) 卵雑炊
喉が痛くても食べやすい雑炊には、栄養価の高い卵に加え、喉の痛みに効くネギや体を中から温める生姜を入れてあげるようにしましょう。
固形物が食べづらい場合は、野菜を煮込んで攪拌したスープでも良いので、豆乳など良質なタンパク質も加えて温かい野菜豆乳スープがオススメですよ。
そして、ウイルス性胃腸炎を早く治すためにも、消化の良い食材を選ぶようにし、麺類であればうどんよりも蕎麦を選ぶなど、こまめな気遣いが大切です。
2) とろろ
免疫力をUPさせ、つるっとしていて食べやすいとろろもオススメです。
キュウリやナス、青じそなど体の熱を冷ます夏野菜を細かく刻んで和えて、とろろをかけて食べると、熱を抑え、症状が悪化しないよう体の回復をサポートしてくれますよ。
3) アイスクリーム
熱が高く食欲も低下し、満足に食事をとれない場合は、卵を使ったバニラのアイスクリームなどでも水分補給になり、効果的です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、プール熱で嘔吐や咳があるときの対処法や注意点、原因について詳しくお伝えしました。
まず、プール熱ではのどの痛みが悪化し咳が出ることや、ウイルス性胃腸炎にかかって嘔吐する場合もあり、注意して対処する必要があるのでしたね。
そして、対処法には、まずは医師の診断の上で学校などへの出席を停止し、プールに入った直後の感染の場合は施設へ連絡をするとさらなる感染を防げるということでした。
また、プール病はくしゃみなどの飛沫感染や便を通じた糞口感染でうつるため、一緒に入浴することやタオルの共用は避け、マスクや手洗いを徹底し安静にすると良いのでしたね。
それから、嘔吐などで脱水症状にかかることもあるので、食事や経口補水液などでまめに水分を補給すると良いとのことでした。
免疫力が下がると他の病気への感染も心配されるので、普段から元気な体作りをして、夏の感染症に負けないようにしましょうね!
スポンサーリンク
プール熱の感染や再感染をきちんと防ぐにはどうしたら?
プール熱に感染すると、子供は登園できなくなりますし、大人がかかると仕事に影響が出て大変なことになりますよね。
なので、感染や再感染はできれば避けたいところですが、実際は手洗いやうがいを徹底したところで、ウイルスが体に入ってくるのを100%防ぐことなど、無菌室に入らない限り不可能です。
それでは、どうしたら良いかというと、ウイルスが体に入ってきてもウイルスを退治できる体にしておけばよいのです。
つまり、人間が自然にもっている免疫力をしっかり高めておければ、たとえプール熱の原因ウイルスに感染しても発症しないので怖くありません。
そこで、続いて免疫をつける最も効率の良い方法についてご紹介いたします。
↓↓↓
「プール熱に対する免疫をつける最も効率的な方法!」
プール熱に関する他の記事はコチラ!?
・プール熱の結膜炎への目薬で市販のオススメ!目やにでうつる?
・プール熱が乳児にかかった時の症状と対処法!注意点もチェック!
・プール熱の初期症状と潜伏期間!治療の際の注意点もチェック!
・プール熱で妊婦の場合の赤ちゃんへの影響!検査の必要はある?
・プール熱の感染力と感染期間!保育園への登園やお風呂についても!